※営業電話はご遠慮ください
【民泊新法】家主居住型と家主不在型の違い、メリット・デメリットについて簡単に解説
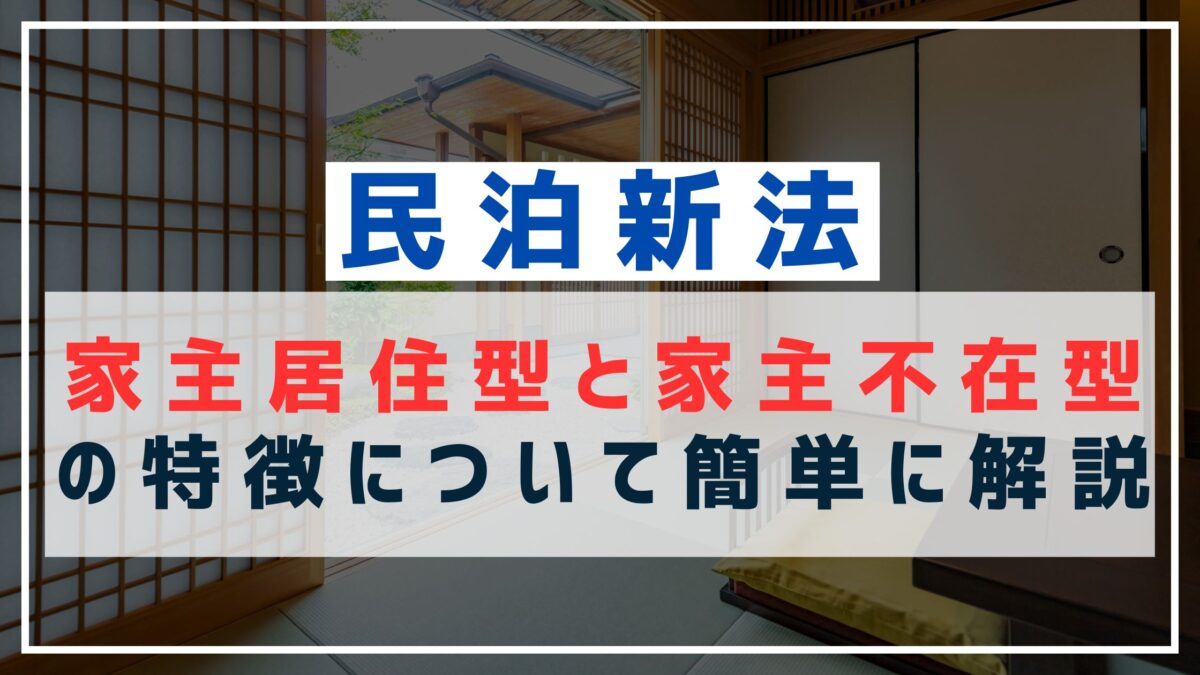
住宅宿泊事業(民泊新法)では、民泊運営を「家主居住型」と「家主不在型」の2つに分類しています。法令上ではこれらの定義はありませんが、両者には運営形態や規制内容に違いがあり、それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解することが重要です。
「家主居住型と家主不在型」の特徴及びメリット・デメリット

家主居住型
家主居住型とは、特定の人が現在生活している家屋を指し、法令上の「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」に該当します。
特徴
- 家主が物件に居住しながら、その一部を民泊として提供する形態
- 家主が宿泊者と同じ建物内に滞在する必要がある
メリット
- 運営の柔軟性
家主が現場にいるため、宿泊者への対応が迅速に行える、観光情報の提供やトラブル対応がしやすい点が魅力です。 - 規制が緩和されるパターンもあり
家主不在型と比較すると、消防設備等の規制が緩和される場合があります。
具体的には、家主居住型で、なおかつ宿泊施設の床面積が50㎡以下の場合、消防法上では一般住宅と同じ扱いとなります。このため、各部屋やキッチンなどに住宅用火災警報器が適切に設置されていれば問題ありません。
ただし、床面積が50㎡を超えると、後述する旅館やホテル等の宿泊施設と同等の扱いになってしまいます。
デメリット
- プライバシーの確保が難しい
家主と宿泊者が同じ建物内に滞在するため、お互いのプライバシー確保に課題が生じる場合があります。 - 運営スペースの制限
家主が居住する部分を除いた限られたスペースでの運営となるため、大人数の宿泊者を受け入れるのは難しい場合があります(収益減のリスク)。
家主不在型
家主不在型とは、その名の通り「宿泊者が滞在している間に家主(届出者)が不在」になるパターンです。法令上の「入居者の募集が行われている家屋」「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」に該当します。
前者は住宅宿泊事業を運営している際に、その物件を売りに出したり、賃貸の募集をするなど、入居者の募集を行っている家屋のことで、後者については別荘やセカンドハウスなど“生活の本拠として使用していない”家屋を指します。
民宿ビジネスを行う場合、そのほとんどが家主不在型での運営となるでしょう。
特徴
- 家主が物件に居住せず、物件全体を民泊として提供する形態
- 家主は現場に不在であり、管理は外部業者やITシステムを利用して行うケースが一般的
メリット
- 運営スペースの自由度が高い
家主が物件全体を利用できるため、大人数の宿泊者や家族連れのニーズに応えることが可能です(収益増に期待)。 - プライバシーの確保
宿泊者が物件全体を利用できるため、宿泊者間でのプライバシーが保たれやすいです。
デメリット
- 規制が厳しい
家主不在型の場合、床面積の多寡にかかわらず消防法では旅館やホテルなどの宿泊施設と同じ扱いになります。そのため、一般住宅とは異なる消防設備(誘導灯や消火器など)を設置する場合もあるため、初期費用が高くなる可能性があります。 - 運営コストが高い
家主が現場にいないため、原則住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する必要があり、費用負担が増える可能性があります。また、宿泊客のトラブル対応が遅れることも考えられます。
管理業務の委託について※補足

上記の通り、家主不在型の場合、基本的に住宅宿泊管理業務を管理業者に委託する必要がありますが、家主不在型に該当する場合も以下のケースでは委託が不要です。
- 「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在(生活必需品の購入等で外出する時間で、原則1時間)」
- 「管理業務を業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合※」
また、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者で、自ら住宅宿泊管理業務を行う場合も不要です。
なお、届出住宅の居室の数が「5を超える」場合は管理業者への委託が必要になります。
※「住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物もしくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき(住宅宿泊事業者がその届出住宅から発生する騒音等による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く)」かつ「届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が5以下であるとき」の両方を満たす場合
まとめ
繰り返しになりますが、それぞれの特徴は以下の通りです。
- 家主居住型
→宿泊施設の床面積が50㎡以下であれば、消防法上は一般住宅と同じ扱いになるため、初期コストを抑えられる
→小規模で柔軟な運営が可能である一方、プライバシーの確保が課題に
- 家主不在型
→消防法の規制や管理業者への委託費用などコストの面で負担が増える可能性がある
→宿泊客に対して広い運営スペースやプライバシーを提供することができる
民泊運営を成功させるためには、物件の床面積や運営方針を踏まえたうえで、最適な運営形態を選択することが重要です。
家主居住型と家主不在型について解説しました。皆さまのご参考になれば幸いです。
当事務所では、民泊ビジネスの開業手続きサポートを承っております。もしご不明・お困りごとなどありましたら、お気軽にご相談ください。
◆対応地域◆
■神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、箱根町など
■東京都
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市羽村市、あきる野市、西東京市など
その他、「千葉県」「埼玉県」からのご相談も受け付けております。
