※営業電話はご遠慮ください
旅館業法の特例「特区民泊」とは? 特徴、メリット・デメリットを分かりやすく解説
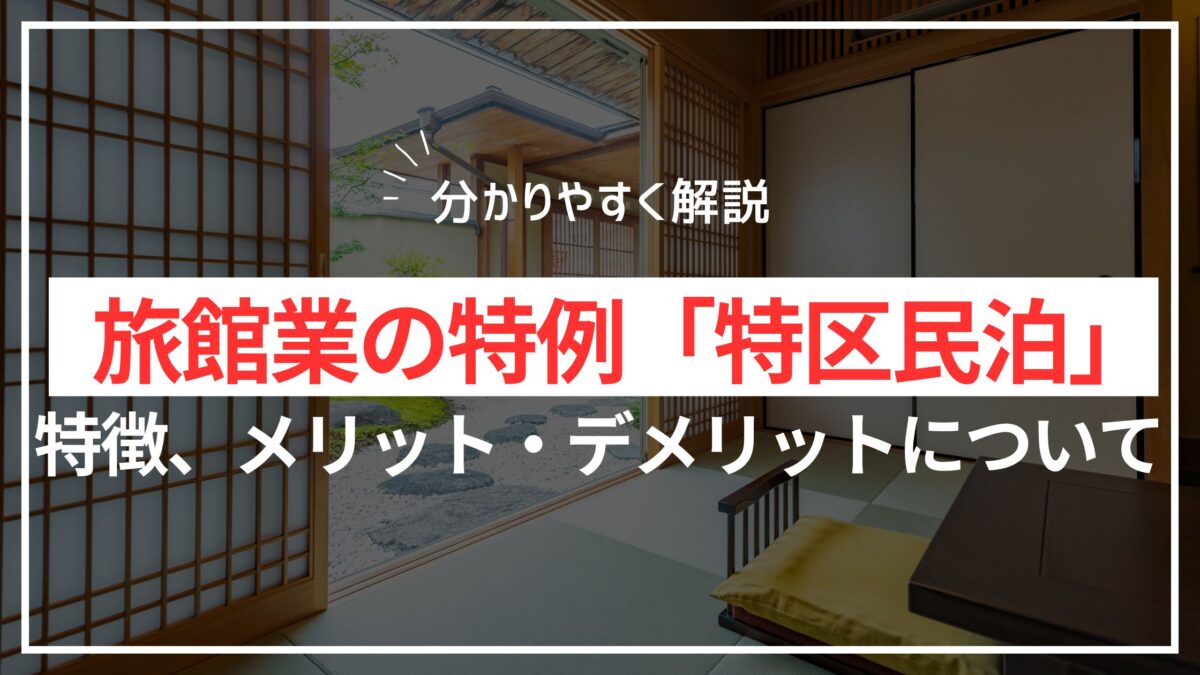
目次
特区民泊とは?
特区民泊とは、「国家戦略特別区域法」に基づき、政府が指定した特区(国家戦略特別区域)において、条例によって認められた民泊営業のことをいいます。正式には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」と呼ばれ、地域限定・日数制限の緩和など、他の民泊制度よりも柔軟な運用が可能です。
特区民泊を行うには、該当地域の自治体へ事業認定申請を行い、必要な設備基準や管理体制を整備したうえで認可を受ける必要があります。
現在、東京都大田区、大阪市、新潟市、大阪府、北九州市、千葉市、福岡市などの自治体が特区民泊を認めています。
住宅宿泊事業(民泊新法)と旅館業との違いは?
スクロールできます
| 住宅宿泊事業(民泊新法) | 特区民泊 | 旅館業(簡易宿所営業) | |
|---|---|---|---|
| 手続き方法 | 届出制 | 認定 | 許可制 |
| 営業可能地域 | 全国 (住居専用地域も可能) | 国家戦略特区の指定区域のみ (住居専用地域も可能) | 全国 (住居専用地域は不可) |
| 最低床面積 | 1人あたり3.3㎡以上 | 原則、1部屋の床面積が25㎡以上 | 33㎡以上 (宿泊者数が10人未満の場合→3.3㎡×人数) |
| 営業日数 | 年間180日以内 | 制限なし (2泊3日以上の滞在が条件) | 年間365日可能 |
| 消防設備 | あり (緩和措置あり) | あり (6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要) | 必要 |
| 手続きの難易度 | 低 | 中 | 高 |
住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)は届出制であり、比較的始めやすい反面、年間180日以内の営業制限があります。
一方、旅館業は営業日数の制限がなく、法的には最も安定的に営業可能な制度です。特区民泊はその中間に位置し、地域限定ながらも柔軟な営業ができる点が特徴です。
特区民泊の特徴とは?
特区民泊には以下のような特徴があります。
- 営業日数の上限なし(ただし最低宿泊日数の制限あり)
たとえば東京都大田区では「2泊3日以上」の宿泊から受け入れ可能です。 - 住宅の活用が可能
元が住居である建物を使って運営できるため、参入ハードルが比較的低い。 - 自治体独自の認定制度
事業者は所定の申請書類を提出し、構造設備基準・管理体制などについて審査を受けます。 - 多言語対応や非常時対応など、外国人旅行者への対応が求められる
インバウンドを前提とした制度であるため、ガイドラインの中に「外国語案内」「緊急連絡体制」などの整備が求められます。
特区民泊のメリット・デメリット
メリット
- 180日の営業制限がない(旅館業に近い)
- 住宅を利用できるため、建築コストが抑えられる
デメリット
- 実施可能な地域が限られている
- 2泊3日以上など、短期利用の制限がある
- 認定基準や手続きが自治体ごとに異なり、専門的な知識が必要
- 設備・管理面で高いハードルを課す自治体もある
まとめ
特区民泊は、旅館業のように安定した営業が可能でありながら、住宅宿泊事業法に比べて柔軟な運営ができる中間的な制度です。ただし、地域限定・制度の複雑さ・認定ハードルの高さなど、導入にあたっては十分な準備が必要です。
民泊を検討している方にとって、「特区民泊」は非常に魅力的な選択肢となり得ますが、適切な行政手続きを踏まなければ認定は得られません。特に、地域ごとの条例や基準を正しく理解し、建物の用途や構造、管理体制を整えることが成功の鍵です。
