※営業電話はご遠慮ください
旅館業を営業するにはどんな手続きが必要? 必要書類・許可要件などを解説
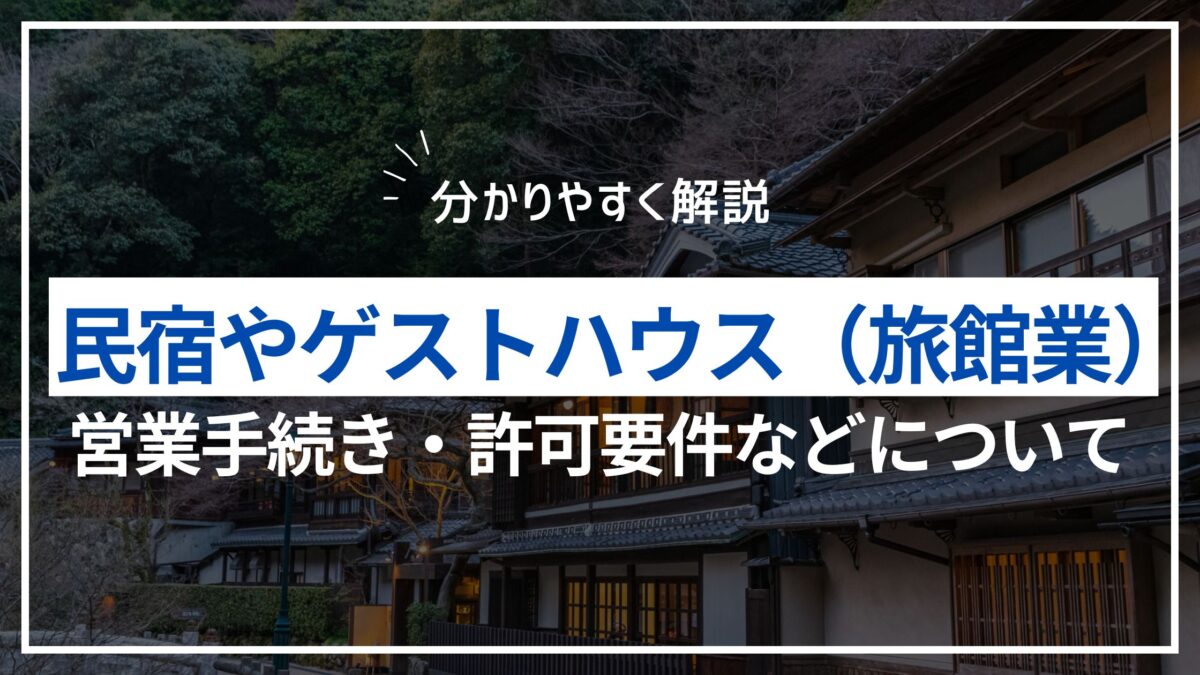
旅館業許可について
ホテルや民宿、ゲストハウスなどの旅館業を営むには、都道府県知事あるいは市長・区長の許可を受ける必要があります。当記事では、許可取得に必要な要件、提出書類、手続きの流れなどについて解説します。
法律上の旅館業は3種類

旅館業は、宿泊施設を提供し、宿泊料を受け取る事業を指します。法律上、旅館業にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や許可基準が異なります。
1.旅館・ホテル営業
旅館業法では、ホテル営業を以下のように定義しています。
この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
旅館業法第2条2項
特徴
- 一般的なホテルや旅館のイメージ。
- 客室は個室が中心で、共用スペースも充実していることが多い。
- ビジネスホテルから高級ホテルまで、さまざまな規模やタイプの施設がある。
2. 簡易宿所営業
簡易宿所営業は、法律で以下のように定義しています。旅館やホテル営業に比べ、手軽さと安価な料金が特徴であり、後述する営業に必要な許可要件も比較的緩やかとなっています。
この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
旅館業法第2条3項
特徴
- 複数人で宿泊場所を共同利用するタイプ。
- 民宿、ゲストハウス、カプセルホテルなどがこれに該当。
- 簡易的な設備で、素泊まりを提供する施設が多い。
3.下宿営業
下宿営業は、「施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されています。宿泊期間が1か月以上となるケースは稀であるため、詳細な説明は以下の内容含めて割愛いたします。
補足(用語の定義)
営業とは
施設の提供が「社会性をもって継続反復されているもの」とされています。
人を宿泊させる営業とは
- 施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること。
- 施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと。
とされています。部屋の衛生管理が住民自身に委ねられているアパートなどの貸室とは、この点が異なります。
旅館業許可の申請要件

旅館業を取得するための主な要件は以下の通りです。ただし、各都道府県によって独自のルール(通称:上乗せ条例)が定められている場合があるため、ここでは一般的な要件についてご紹介いたします。
人的要件(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業共通)
以下に当てはまる申請者(法人の場合は役員含む)は、許可申請をすることができません
旅行業法3条2項
- 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
- 第八条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して三年を経過していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
場所的要件(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業共通)
旅館業はどこでも営業できるわけではありません。旅館業法3条3項では営業可能な地域に関するルールが定められています。
第一項の許可の申請に係る施設の設置場所(=宿泊施設の場所)が、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様(都道府県知事等は許可を与えないことができる)とする。
旅館業法3条3項
①学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除くものとし、次項において「第一条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)
②児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。)
③社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定めるもの
要するに、「学校(幼稚園、小学校、中学校など)」や「保育所」の周辺約100m以内で、旅館施設の営業がその保護施設の環境を著しく害するおそれがあると判断された場合、許可を取得することはできません。この判断は、保健所が当該保護施設に意見を照会し、同意を得られるかどうかによります(※同意を得られても、何かしらの条件を付けられる場合があります)。
そのほか、都市計画法では宿泊施設の立地条件(用途地域)が定められており、営業可能な地域は「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」の6種類に限定されています。
構造的要件
構造に関する要件については、営業形態によって異なるルールが定められています。
旅館・ホテル営業
旅館業法施行令第1条
- 客室の床面積は、7㎡(寝台を置く客室にあつては、9㎡)以上であること。※1客室の床面積
- 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
- 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
- 適当な数の便所を有すること。
- その設置場所が法第三条第三項各号(※学校や保育園等)に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興(※ショーやダンス等)若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
分かりやすくまとめると、以下の通りです。
- 1客室の床面積は7㎡(ベットを置く客室では9㎡)以上
- 宿泊客と適切な面接ができる設備(「玄関帳場(フロント)」or「ビデオカメラ等で本人確認ができるICT設備)」等を設けること
- 換気・採光・照明・防湿及び排水の設備、お風呂・洗面所・トイレが設置されていること。
さらに具体的な要件については、各自治体の条例等で定められています。
簡易宿所営業
旅館業法施行令第1条
- 客室の延床面積は、33㎡(法第三条第一項の許可の申請に当たって宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
- 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること。※いわゆる二段ベッドのこと
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
- 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
- 適当な数の便所を有すること。
- その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること
床面積の最低限度の数値や、フロントの設置が義務付けられていない(自治体によっては上乗せ条例あり)ことから、旅館・ホテル営業に比べて許可要件はかなり緩やかです。そのため、民宿サービスを提供するのに最も適した形態が、この簡易宿所営業といえるでしょう。
その他法令の遵守事項
このほか、火災や地震などの防災リスクに対応するため、建築基準法や消防法の規定を遵守する必要があります。
その内容は多岐にわたりますが、たとえば、もともと住宅として使われていた建物を旅館施設として再利用する場合、用途変更(一般建築物から特殊建築物)に伴い、一般建築物よりも厳しい安全基準を満たさなければなりません。
必要書類
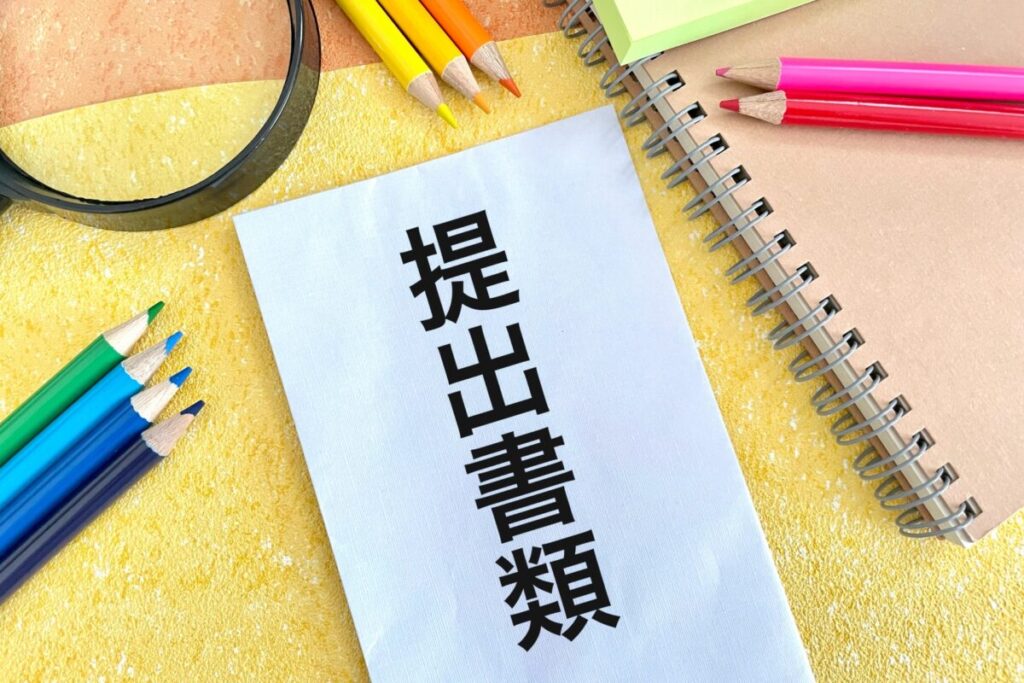
旅館業の営業許可を申請するには、許可申請書のほか、さまざまな添付書類が必要です。また、自治体によっては追加書類が求められる場合もあります。ここでは、神奈川県小田原市で許可申請を行う場合の必要書類等をご紹介いたします。
| 申請書・添付書類 | 備考欄 |
|---|---|
| 旅館業営業許可申請書 | |
| 施設の配置図 | 敷地と道路の位置関係及び施設の配置が分かる図 |
| 施設の各階の平面図 | ①各階全体の平面図(寸法を記載) ②客室の内法面積が分かる図面 |
| 施設の四面の立面図 | 立面図、透視図、もしくは施設の外観の写真 |
| 玄関帳場(フロント)の詳細図 | フロントの構造が分かる立面図又は写真 ※フロント機能を代替する設備を有する場合は、フロント代替設備調査票 |
| 階層式ベッドの断面図 | 階層式のベッドのある客室がある場合は、その断面図 |
| 浴槽等の構造図面 | ①入浴設備の調査票 ②配管系統図(ろ過器、集毛器、塩素注入機等の位置関係や循環湯の補給場所等、入浴設備の構造が分かるもの)、ろ過器の仕様書(ろ材、処理能力が分かるもの)、浴槽容量算定図 |
| 営業施設付近の見取り図 | 縮尺1/3000 以上の地図※「地図見本縮小版」を参照して作成 |
| 標識の設置場所を記載した書面 | 当該設置場所が公衆の見やすい場所であることが分かる図面及び配置図 |
| 洗面用水・浴用水の水質検査成績書の写し (洗面用水・浴用の水が水道水以外の場合) | 水質検査成績書の写し |
| 定款の写し、寄付行為の写し又は規約の写し (法人の場合) | |
| 消防関係手続書類 | 適合通知書、検査済証、消防署の収受印が押印してあるもの等 |
| 自主管理の手引書 | 営業時間、システム・料金等を記載 |
| 商業登記事項証明書 (法人の場合) | 法人の場合は全役員分 |
| 委任状 | 行政書士が手続きを代理する場合 |
手続きの流れ

お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。
希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。
申請書や図面等の添付書類を作成し、届出住宅の所在地を管轄する行政機関へ提出します。
監視員が、申請内容と相違ないか現地を調査
許可が下りるまでの期間は、小田原市の場合15日間以内(土日祝・年末年始休暇を除く)とされています。
※施設が学校等の敷地から概ね100m以内の距離がある場合は、許可・不許可の決定までさらに1か月以上かかる場合もあり。
まとめ
旅館業を営業するために必要な手続きなどについてご説明しました。旅館業の開業手続きは、住宅宿泊事業(民泊新法)よりも申請の難易度が高い許可制であるため、注意すべきポイントが多岐にわたります。
当事務所では、上記申請手続きの代行から物件探しのサポートを承っております。旅館業のオープンをご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
◆対応地域◆
■神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、箱根町など
■東京都
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市羽村市、あきる野市、西東京市など
その他、「千葉県」「埼玉県」からのご相談も受け付けております。
