※営業電話はご遠慮ください
市街化調整区域には要注意!? 民泊を始める前に必ず確認すべき都市計画のポイント
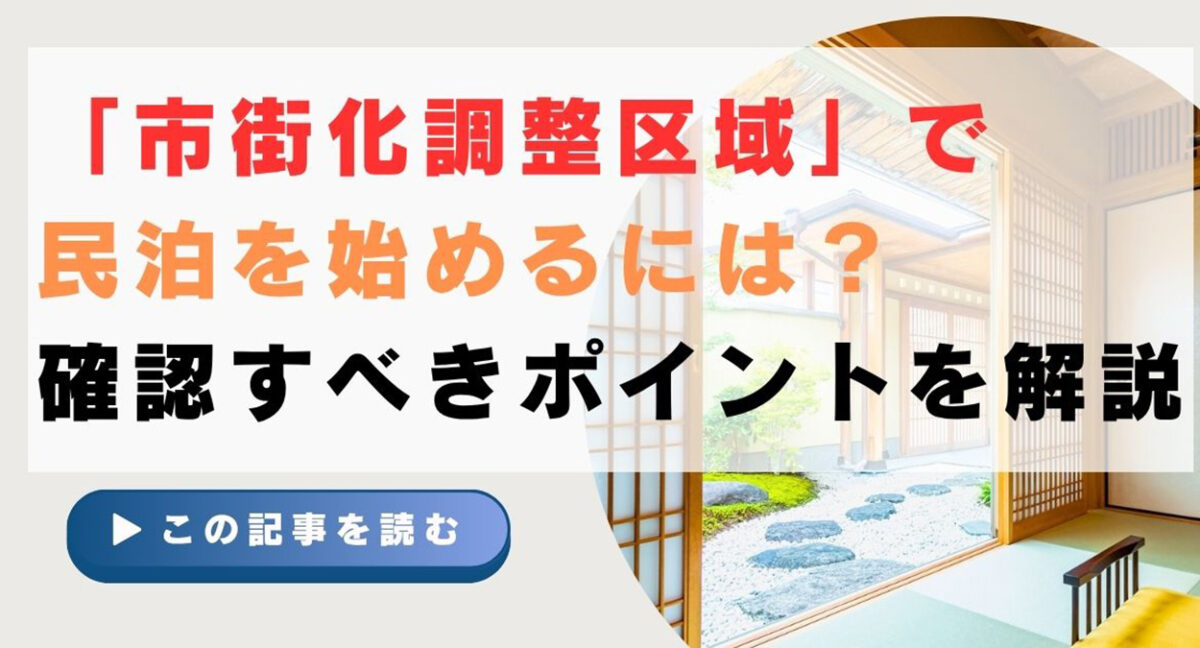
民泊(住宅宿泊事業)を始める際には、建物の立地するエリアが都市計画上どのような区域に指定されているかを確認することが重要です。特に「市街化調整区域」と呼ばれるエリアでは、民泊営業に大きな制約がかかる場合があるため、慎重な判断が求められます。
本記事では、民泊を検討している方向けに、市街化調整区域に関する基本的な知識と注意点をわかりやすく解説します。
都市計画区域とは?
「都市計画区域」とは、都市の健全な発展や秩序ある整備を図るために、国や自治体が都市計画法に基づいて定める区域です。市町村の大部分はこの都市計画区域に含まれており、用途地域や建ぺい率・容積率、開発行為の規制などが設けられています。
都市計画区域の外ではこれらの規制が緩やかになりますが、区域内では土地利用に対する規制が明確に定められています。都市計画区域はさらに、以下の2つに分類されます。
「市街化区域」と「市街化調整区域」とは?
都市計画区域は次の2つに区分されます。
● 市街化区域
すでに市街地を形成している区域、または今後10年以内に優先的に市街化を進めるべき区域です。この区域では住宅や商業施設、宿泊施設などの建築が原則として自由に可能で、民泊営業も許可要件を満たせば比較的スムーズに行えます。
● 市街化調整区域
一方、市街化調整区域は、無秩序な開発を防ぐために市街化を抑制すべき区域とされています。原則として新たな建築や開発行為が制限されており、住宅・店舗・宿泊施設などの用途変更や新築は、原則として許可されません。
「市街化調整区域」で民泊を始めるにはどうしたらいいのか?
1. 線引き“前”に建築された建築物か
都市計画における「線引き」とは、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けることを指します。その線引きがされる前に建築された建物であれば、都市計画法の制限がかかる以前の建築物であるため、民泊を営業することができます。
2. 属人性のある建物か
市街化調整区域では、属人性のある建物であるかどうかも確認しなければなりません。
これは、特定の権利を有する人が居住している住宅のことで、たとえば、農林や漁業従事者のための住宅や本家から独立した住宅(分家住宅)が「属人性のある建物」に該当します。
属人性のない建物であれば、住宅宿泊事業を行うことができます。その一方で、属人性のある建物の場合は「家主居住型or家主不在型かどうか」で判断が異なるケースがあり、原則家主居住型でなければ事業を行うことはできません。

なぜなら、「属人性がある住宅」にもかかわらず、特定の権利を有する人がいない住宅(空き家など)で住宅宿泊事業を営業することは、本来の趣旨と異なる使用方法だからです。
3.用途変更は必要か
住宅宿泊事業を行う場合、建物の用途は原則として「居宅」、旅館業(ホテル・簡易宿泊所)を行う場合は「旅館・ホテル」となっている必要があります。
特に市街化調整区域内では、建物の用途変更が都市計画法によって厳しく制限されているため、あらかじめ現在の用途が上記に該当しているかを確認しておくことが重要です。
4. 自治体独自の運用ルールを確認
市街化調整区域の運用は自治体ごとに差があり、地域の都市計画審議会で判断されることもあります。一定の条件のもとで民泊が可能となるケースもあるため、事前に市町村の都市計画課や建築指導課に相談することが必須です。
確認の流れ
まず③自治体独自の運用ルールを確認した上で、民泊を始めたい住宅が①線引き前に建築された建築物かどうかチェックし、
・線引き前であれば民泊OK
・線引き後(=市街化調整区域)に建てられた住宅の場合は、属人性の有無を確認。これを受けて、営業形態(家主居住型or不在型)も再考する
…といった流れで確認しましょう。
まとめ
市街化調整区域においては、民泊営業には大きなハードルが存在します。都市計画法により新たな開発や建築が制限されており、たとえ既存の建物があったとしても、民泊の営業が認められないケースも考えられます。
民泊を始める際には、以下の点を必ず確認しましょう:
- 線引き前に建築された建築物か
- 属人性のある建物かどうか
- 自治体における個別の運用基準
安易に調整区域の物件を取得・契約する前に、必ず専門家や自治体に確認を取り、後のトラブルを未然に防ぐことが大切です。
